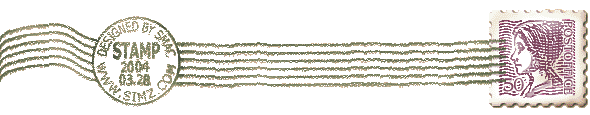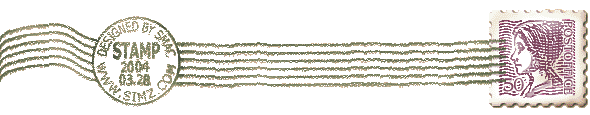「ええぇぇぇぇぇぇっ!」
大庭詠美が突如として発した素っ頓狂な大声は、都内某所にある、煉瓦造り
でシックな雰囲気を持つ店内と、イタリア帰りのシェフによる本場仕込み料理
が評判のリストランテに響き渡った。
驚嘆を内包した奇声は窓ガラスをビリビリと震動させ、周囲の席に座してい
た客達が、何事かと一斉に彼女を見る。
「……」
彼女の対面に座っていた猪名川由宇は、おもむろに座席から立ち上がると、
利き手を振り上げた。
「やかましいわっ!」
歯切れの良い関西弁のイントネーション、それに「ゴンッ!」と、鈍器のよ
うな物で固形物を叩いたような音がした。
「ふみゅっ!」
愛玩動物の鳴き声にも似た短い発声と共に、テーブルへ突っ伏す詠美。
「ったく、毎回毎回、ウチらを好奇の目に晒しよって…」
付いた埃を払うが如く、掌をパンパンと叩きながら腰を下ろす由宇。
「しっかし…ま、詠美やのぅても驚くわ。まっさか、あんたがメジャーデビュー
とはな…」
そしてテーブルの上に肘をつき、両手を組み合わせて顎を乗せると、自分の
横に座っていた長谷部彩を横目に見た。
「……」
彩は少しばかりはにかんだ表情で、テーブルの中央にある大皿に盛られたペ
ンネを、フォークとスプーンで自分の取り皿へと移していた。
トマトソースで味付けされたペンネだ。
料理の上に添えられた飾り用バジルの緑が、トマトソースの赤とほど良くマッ
チして食欲を誘う一品である。
「運が…良かっただけですから…」
「まぁたまた、謙遜しおってからに。…けど、あんたの作風はウチやこの大馬
鹿詠美と違って、オリジナル向きやったからなあ。…ある意味当然の結果やろ」
彩と同じように、ペンネを自分の皿へ取りながら、由宇が言う。
その言葉に、彼女はまた少し照れた表情になる。
季節は、もう春。
少しばかり早く開花した桜の花が闇夜に浮かび上がる季節。
由宇、彩、詠美という“いつもの”三人組は、都内で割と評判の良いイタリ
ア料理店に来ていた。
そこで、夜景を楽しみつつイタリア料理のコースを堪能していると、不意に
彩が一言漏らす。
「わたし、今度商業誌にデビューすることになりました」
由宇と詠美は、思わず食べる手を止めて、目を丸くした。
彼女の言っている意味が判らなかったのだ。
「…あ、これ名刺です」
おずおずと、彩は名刺を差し出す。
今一つ状況が飲み込めないまま、小さな紙片を受け取る二人。
いち早く、事態を己が中で整理した由宇は、「へぇ…」と感心する。
が詠美は、より激しく混乱し、思わず大声が口を衝いて出たために、先ほど
由宇の手によって強制的に沈黙させられたのだった。
「しっかし、このペンネーム、すっごいなー」
彩から差し出された名刺を掌で器用に弄びながら、由宇が呟く。
名刺には、彩の商業誌用ペンネームと電話連絡先、そしてメールアドレスが
記されている。
恐らく、業界関係者へ配布するために作った物であろう。
由宇が注目しているのは、そのペンネーム部分だ。
「…播磨八雲…か」
その名に、「えも言われぬ」といった感じの複雑な表情を浮かべる由宇。
「まー、なんちゅうか、毎週水曜発売の講談社漫画雑誌読者をあからさまに狙
っているちゅうか、嫁入りしたん? ちゅうか、ネットの巨大匿名掲示板です
ぐさまスレが立ちそうな名前やなあ…」
「一応、柳田国男ゆかりの地である播磨と、小泉八雲をかけたペンネームです。
深い意味は特にありません」
由宇の言葉に、彩がそう涼しげに応える。
「あと、獣魔術も、陸奥圓明流も使えませんから…」
(ど、どこまで本気なんやろか?)
由宇は彩の真意を探ろうとしたが、その瞳は深く底が見通せないので、あま
り深くは突っ込まなかった。
「そんなことよりよっ!」
突然、今までテーブルに突っ伏していた詠美が顔を持ち上げた。
「ぬぁんで、この詠美ちゃん様を差し置いて、あんたなんかに商業デビューの
お声がかかるのよ! いかない、いかないっ! ずぇんずぇん納得いかないわ
よっ!」
嫉妬と敵意を剥き出して喚く詠美の頭を、由宇は「やかましいわ」とメニュー
の背で強めに叩く。
「ふみゅ! なにすんのよ、この温泉パンダ!」
叩かれたところを手でさすりながら、涙目で詠美は由宇を見た。
「あんなぁ、詠美」
由宇は自分の前に置かれた皿から、一つのペンネをフォークで突き刺すと、
自分と詠美の前に差し出した。
「な、なによ…」
彼女の意を読めず、少しばかり頭を引く詠美。
「彩がメジャーデビューできたんは、ちゃんとした理由あってのことや」
「どんなわけよ?」
「それはな、ウチやあんたの作風は、言うなればこのペンネにつける調味料み
たいなもんや。素材に様々な手を加え品を加え、料理として完成させる。…せ
やけど彩の作風は、このペンネそのもの。素材そのものを作るって感じなんよ。
うちの言ってること判るか? つまり、そういうことなんや」
少しばかり自分に酔ったようなしたり顔で、詠美を説教する由宇。
「なに言ってんのよ、わけ判んないわ。ちゃんと日本語で話して下さーい…っ
て、あははっ、ごっめーん、パンダに日本語は難しかったか」
が、詠美には由宇の言わんとしているところが、一欠片も伝わらなかったよ
うだ。
果たして詠美の言語理解能力が弱いのか、由宇の比喩が元から懸け離れすぎ
て相手に伝わりにくいのか。
ヒクッ、と由宇の頬が引きつった。
「ほう、ウチの高尚な例えが理解できんとは…。いやいや、スマンかったな、
詠美。あんたと会話するのには、幼稚園のお子ちゃまレベルまで日本語レベル
を下げなあかんこと忘れとったで、な? え、い、み、ちゅ、ぁ、ん」
ピキッ、と詠美のこめかみが引きつけを起こす。
「なに? 山奥で笹食べるか温泉で居眠りしてるしか脳がない田舎パンダが、
この都会育ちでセレブな詠美ちゃん様に喧嘩売るってぇの? ふふーん、いい
わよ、買ってやろうじゃないの。角と飛車の違いを、その貧相な身体に教えて
あげるわよ!」
「貧相やない! ウチはちょっと線が細いだけのスレンダーボディや! あと、
角と飛車の違いってなんやねん。ひょっとして、『格の違いを教えてやる』っ
てゆぉうとしてたんか? だとしたら…あははっ、相当にお間抜けさんやで」
「かちーんっ! ムカツク、ムカツクっ! ちょぉぉぉムカツクっ! なにさ、
ちょっとくらい言葉知ってるからって!」
「アホ、ちょっとやない。た、く、さ、ん…知っとるんや。どこぞのアホな子
と違(ちご)うてな」
その一言が決め手となった。
由宇の発した言葉の前に、詠美の頭の中から「ブチーン!」と、限界まで伸
ばしたゴム紐を鋏で切ったような音がした。
「泣かす泣かすっ! マウント取ってから、ボッコボコのプーにぶちのめして
やるっ! もう泣いたって許してやらないからねっ!」
「おう、上等やっ! かかって来さらせ!」
一触即発の均衡が破れ、テーブルから身を乗り出し、二人がお互いに掴みか
かろうとした正にそのとき、彩は手にしていたフォークを慣れた手付きで逆手
に持ち変えると、そのまま目にも止まらぬ勢いで由宇と詠美、両者の間の空間
へ風切り音と共に振り下ろす。
ガッ、と金属で木を穿つような音がして、テーブルに突き刺さる銀色のフォー
ク。
イィィィィィン…。
突き刺さった際の余韻か、フォークは微かに鳴動音を発していた。
それは、共鳴音を奏でている音叉のような印象を、見る者に与えた。
「……」
「……」
両者の空間を穿つように突き刺さっているフォークを前にして、由宇と詠美
はすっかり毒気を抜かれ、彼女らは同時に彩の方へと恐る恐る頭を動かす。
彩はいつもの、深山にある湖のように静かな面持ちで、「他の人に迷惑です」
とだけ告げた。
「そ、そやな! お、お客はウチらだけやないんしな! あ、あはは…」
「ちょ、ちょっとオイタが過ぎちゃったわよね」
少しばかり前までの剣呑な雰囲気がどこ吹く風か、二人は場を取り繕うよう
なぎこちない笑みを浮かべながら、身体を席に戻す。
「すみません、ピッツァ・マルゲリータを…。それと、もずく」
そして彩はウェイターに声をかけると、何事もなかったように追加のオーダー
を依頼したのであった。