オレは目を閉じて、ゆっくりと深呼吸をした。
すると鼻腔から潮の匂いを嗅ぎ取ることができる。
耳を澄ませるまでもなく、波の音が絶え間なく聞えてくる。
ゆっくり歩けば、ビーチサンダル越しに足の裏から感じる砂の独特の感触。
そしてシャツをはためかせるようにして全身を駆け抜けていく風だけが、今のオレの感じられる全て。
少し前を歩く彼女が感じているものはこれだけなのだろうか。
それとも、オレには判らないものまで感じ取れているのだろうか。
「浩平く〜ん」
「おおーっす」
先日、誕生日プレゼントとしてオレが贈った服を着ている彼女の呼ぶ声がしてオレは目を開けた。
先を行く彼女はオレが遅れていることに気付いたらしく、振りかえって大きく手招きをしていた。
こんな足場の悪い砂浜でよくもまあ、杖も何もなくて歩けると感心する。
オレなら転ぶかぶつかるかしてしまいそうで怖くて下手に進めない。
だが、彼女は迷うことも躊躇うこともなく先を行っていた。
今度は深呼吸の代わりにため息をついた。
彼女は、すごい。
6月。
時たま真夏のように太陽がギラつく暑い日があったりする、不安定な天候と気まぐれな暖寒から暦で単純に割りきれるような季節を味わえない月。
この時期ぐらいになるともう五月病だとか、憂鬱だのだるいだの言っていられる時期ではないのだが、どうしても毎日のように振り回される天気によって気分が優れないことが多い。
ニュースではこの辺りは梅雨入り宣言をしたとか言っていたが、幸いにして今日はとても良い天気に恵まれていた。
暑い日は暑い日なりの不愉快な程の日射を浴びることで、気だるくなってしまうのだが、ここはアスファルトの上でもなければ、設えの悪い住宅の中でもない。
今日はデートとして電車で数駅離れた海辺に来ていた。
息抜きと称して遊びに誘ったのはオレの方だったが、この場所を選んだのは彼女の方だった。
さっきから見えない彼女の代わりに一帯を見渡せる限り見渡すが、まだ海開きもしていないせいか、オレ達以外人気は全くなかった。
屋台も海の家も勿論ない、寂れた風情を感じさせる場所だった。
これでも真夏になると大勢の人が群がる場所なのだろう。
少し損なことを考えると奇妙な感じもするが、今のオレにとってはどうでもいいことだった。
海。
暑いことを心地良いだけの余裕をもって感じ取ることのできる数少ない場所だ。
着ている物もこんな天気を前提とした薄手の夏服なので、潮風が吹くことで下手をすると肌寒さを覚えかねないほどだった。
そしてこんな折角の晴天に、今日だけはオレは日頃のことをできるだけ忘れることにした。
有り得ない離脱と、有り得ない復帰をオレはこの一年の間に果たしていた。
理由も原因も共に判っているのだが、どうしてこんなことになっとのか、どうしてそんなことができたのかは未だにわからないし、一生わからないことだろう。
世の中には不可思議なことが多過ぎる。
オレの今度の原因もその一つとして自分の中で消化してしまうことにした。
安っぽい言葉だが、奇跡とでも言えば全て万事丸く収まる。
オレさえ我慢し努めて忘れることにすれば。
だが仮に世の中に奇跡が満ち満ちていたとしても、オレの進学までには手が回らなかったらしい。
いや、一日も授業を受けてもいない生徒を呆気なく卒業させる高校の方が実際はどうかしている。
二年の終わりから丁度丸一年程、オレはこの世界とは違う場所で過ごしていた。
それだけにその一年間分の欠席とそれに伴う当然の結果としてオレは留年を覚悟していた。覚悟もなにも当然だと思っていた。
が、オレがこの世界から帰ってきた卒業式の日が終わって数日後、オレの元に卒業式当日欠席した生徒宛として、学校から卒業証書が送られた時は本当にビックリした。
―――浩平君、卒業おめでとう。
オレが還ってきた時、彼女からそう言っては貰ったものの、本当に卒業できているとは思っても見なかった。
髭の仕事は想像を遥かに越えて雑だったらしい。学校に行って調べたところオレの出席率は三年時は皆勤賞で、欠席したのは還ってきた日の卒業式だけだった。
長森や住井、七瀬らかつての同級生に会ってみたところ、みんな三年生でのオレの存在については記憶がないようだった。時折オレの絡んだエピソードを思い出したように喋るがそれらはみな、二年の時の思い出だった。
当然だ、俺はいなかったのだから。
が、記録上でのオレは修学旅行などのイベントを除き、平日は全て登校し、皆勤したことになっている。
三年になってクラス替えがなかったのも幸いした。受験に専念させる為というお題目ではあるが、そのせいで時期が曖昧な想い出を適当に三年の頃とミックスして丸一年のオレの存在の空白が皆からそれ程目立つものではなくしてしまっていた。
この手際の良さはどうしたものだろう。向こうで一年を共に過ごしたみずかの仕事はハッカーなのだろうか。
そんな馬鹿なことを思わないでもない。
流石にそんなみずかでも俺の進学先までは用意してくれなかったらしく、オレは普通に浪人していた。
考えてみれば当たり前の話だ。
卒業式の後に試験を受けられる大学はまずない。二次、三次募集かごく一部の金さえ出せば入れるような定員割れの大学ぐらいだろう。
そしてオレはそんな大学さえ選べるだけの時間など存在しなかったし、そこまでして現役で入らなくてはいけない理由は何一つなかった。
強いて悔しいことは長森達の一年後輩になってしまうことだが、同じ大学にさえ入らなければ気にすることはない。しかも長森はよりにもよって今時短大なんかに入っていたから尚更平気だ。将来有名企業に就職するつもりはないのだろうか。
あいつは今でも会ってオレの顔を見るたびに「浩平が心配だよ」を連発するが、お互いこうして卒業してまでずっと心身ともに成長を見て取れないおまえの方が、よっぽどオレは心配だ。
ま、人のことはいい。
そんな一年間姿を見せなかった居候のオレに対して、久々にじっくりと話す機会があった由起子さんは何故か教育熱心だった。
オレのことを忘れていた負い目――ではないだろうが、オレの存在が消えてからも続けていたらしい貯めていた進学資金の一部を使って、オレを予備校へと通わせてくれた。その代わり、オレの部屋がまるで忌み場所でもあるように封印されていたことについては何の説明もなかった。オレもその事には努めて触れないように心がけた。
元々高校時代から熱心とは程遠い勉強態度をとっていた上に、高校三年の授業を何一つ受けていないオレにしてみれば、この一年の間で回りに追いつくことは相当困難なことではあった。
そんな時に頼りになるのは高校時代の長森のノートだった。
あいつのノートは丁寧な字で書かれているので読みやすいし、本当に判り易く時には蛍光マーカーで、時には余白に張りつけたプリントの内容で理解できるような作りになっていて助かっている。判らないことがあればいつでも聞けるし、何でも答えてくれる。全くもってありがたい。幼馴染はこうあるべしという生きた見本のような存在だ。
そんな還って来てからのオレの財政面での頼りが由紀子さん、勉学面での頼りが長森なら、オレの毎日の癒しの存在は目の前を行く彼女だった。
オレがこうして還ってこれたのも、彼女との約束があったからだ。
…オレはずっと先輩の側に居る。
…何があっても、必ず最後には先輩の側に居る。
オレはそう約束したから。
どんなことがあっても最後には。
必ず。
その思いだけでオレはここにこうして立っている。
笑っていられる。
「浩平君」
「……あ」
「えいっ!」
「わっ!?」
いきなり、顔に何かかけられた。
しょっぱい。
海水だ。
「先輩! いきなり何を……」
「いきなりじゃないよ〜。浩平君がいくら呼んでも返事しないからだもん!」
笑顔半分、膨れっ面半分といったところか。
彼女が両手ですくっただけの海水の量はシャツまで濡らせていた。
「ああ、悪い。ちょっと感慨に耽ってたんだ」
「随分呼んだんだよ。何度も呼んだのに、ひどいよ」
「ごめんって」
「黙っているからどこにいるのかもわからないし」
「いや、本当にごめん」
オレが謝れば謝るほどすねていく。
「どうせ浩平君なんか私のことどうでもいいんだ」
「そんなことないって」
「本当に?」
「ああ」
「本当の本当に?」
「ああ!」
「本当の本当の本当に?」
「ああ! 本当の本当の本当の本当にだ!」
「じゃあ……今回だけだよ」
「こんなオレを許してくれるのかい? ありがとう先輩!!」
わざとらしい台詞で応じる。
それでも最初から殆ど機嫌なんか損ねていなかったのか、先輩はニコニコ笑いながら聞いてくれた。
「あはは、それにもう『先輩』じゃないよ」
「いや、それはまだ習慣が抜けてなくてさ」
たまに注意されるが半分諦めているのか、それほどしつこくは言ってこない。
「もう、仕方がないなあ」
「どうしても嫌だったら改めるように努力するけど……」
「今は、いいよ」
「え?」
「今はまだ、先輩でもいいよ」
「?」
言っている意味がわからずに戸惑うオレに先輩はニコリと笑った。
「浩平君が私のこと貰ってくれる時までは、まだこのままでもいいよ」
「え? え? え? ……ええっ!?」
「貰ってくれないの?」
「あ、え……」
「うう…ポイ捨てだよ〜 やり逃げだよ〜 浩平君はそんな人だったんだ〜」
「い、いやそんなことは!」
「フフフ……」
慌てる様子が声と気配でわかるのだろう。
とても愉快そうに笑っている。
見事にからかわれている。
「なんだか先輩、意地悪になったな」
「一年も放ったらかしにした冷たい誰かさんのせいだよ」
笑いながらそう続ける。
「そっか……」
「うん。逞しくなったでしょう」
えへんとばかりに胸をはって見せる先輩の姿がとても可愛らしくて、そしてどこかいじらしかった。
「出会ったときからずっと逞しく見えたけど」
「あ、ひどいよ〜」
出会った頃からそうだった。
別に虚勢をはっているわけではない。
無理に明るく振舞っているわけでもない。
けれども先輩はいつも楽しそうにしながら、いつもどこか淋しそうだった。
いや、淋しいと言うよりもいつも不安を抱えて怯えていた。
オレには先輩の苦しさや辛さ、大変さと共にそんな不安や悲しさを知ることはできないし、先輩もあれこれと気遣われたくはないだろう。
だからオレはずっとそんな彼女の側にいたいと思った。
彼女が心の底から笑い続けられるように。
そう誓ったはずだった。
オレがいなかった一年を先輩がどう過ごしたのかはわからない。
他の皆のように都合良く記憶から抜け落ちたわけではない。
先輩だけは、オレのいなくなった一年間を知って過ごしていたのだから。
そうして、一年後にオレ達は卒業式の日の屋上で先輩に再会する。
…ちょっとどころじゃないよ
…ずっと待ってたんだよ…
…毎日待ってたんだよ…
…それなのに
それなのに。
そう、それなのにオレはあの日までずっと、みさき先輩を放ったらかしにしてしまった。
ずっと側にいたかったのに。
いなくてはいけなかったのに。
そう約束したのに。
「………」
「浩平君?」
「ん? 何?」
「…もしかして怒ってる?」
「い、いや全然!!」
しまった。また黙り込んでしまっていた。
「ただその……ええと」
「もしかして、無理してる」
「そうじゃなくてえーと」
オレが大人しくしていることで、不安にさせてしまっているようだ。
「………」
あれこれと考えて、その不安そうな表情をした先輩を見て思いついた。
「実はずっと見ていたんだ」
「え? 何を?」
「それがな、先輩…」
「何なのかな?」
「このようなことは大変失礼な質問だとは、重々承知しているのでござるが…」
先輩はオレの時代がかった似非口調に警戒したように眉を顰める。
「浩平君、何だかおかしいよ?」
おかしくて結構。
そしてオレはすぐにいつもの調子に戻して、
「その、下着つけてるの?」
彼女の剥きだしの二の腕あたりを指で軽く押しつけるようにして、ズバリ聞く。
「…えっ」
固まる。
「………」
「………」
そして暫くして、
「こ、浩平君のエッチ! いきなり何言い出すんだよっ」
オレの言葉を理解したのか、慌てて隙間を手で隠すように両手で自分自身を抱きしめる先輩。
そうすることで質量感のある胸が腕の中で押し潰されているのがわかって、それはそれで大層魅力的だった。
だが、先輩が恥ずかしそうな顔でオレをじっと見つめているので、それを言うのは躊躇われた。
このままもう暫く見続けていたいという純粋な欲望もあったが。
「だから最初に断っただろ?」
そう弁解するが、
「…だからって、そんなこと言うなんてひどいよ〜」
すねたようにそう言うと、下を向いた。
「純情な少年の正直な好奇心とでも呼べば先輩もきっと納得してくれるものと」
「そんなわけないよっ」
詭弁通じず。
まあ、当たり前か。
「うー、そんなこと言われたから急に恥ずかしくなってきたよ」
「オレはちっとも気にならないぞ」
「う〜」
「そりゃあもう全然平気バッチグーだ」
「………」
あ、みさき先輩怒ってる。
流石にちょっとからかいすぎたか。
「…飽きれてるんだよ」
「あ、読まれた」
「もう……浩平君だけだよ」
そう言うと、彼女は表情を緩ませて楽しそうに笑ってくれた。
「いやさあ、さっき散々いじめられたから…」
「絶対にまた今度仕返しするからね」
「うっ……」
先輩は根に持つタイプかも知れない。
いや、全てはオレのせいだとは思うのだが。
「風が強くなってきたね…」
先輩はそう言うと、飛ばされないようにと被っている帽子を片手で抑える。
「そうだな。そろそろ戻ろうか?」
オレの服も騒いだりしているうちにいつの間にか乾いていた。
「うん…キャッ!」
強く吹いた風にスカートが捲りあがりかかり、慌てて右手で抑えつける。
左手は帽子を抑えたままだったから、勢いのあるこの風が収まるまでは身動きが取れなくなっていた。
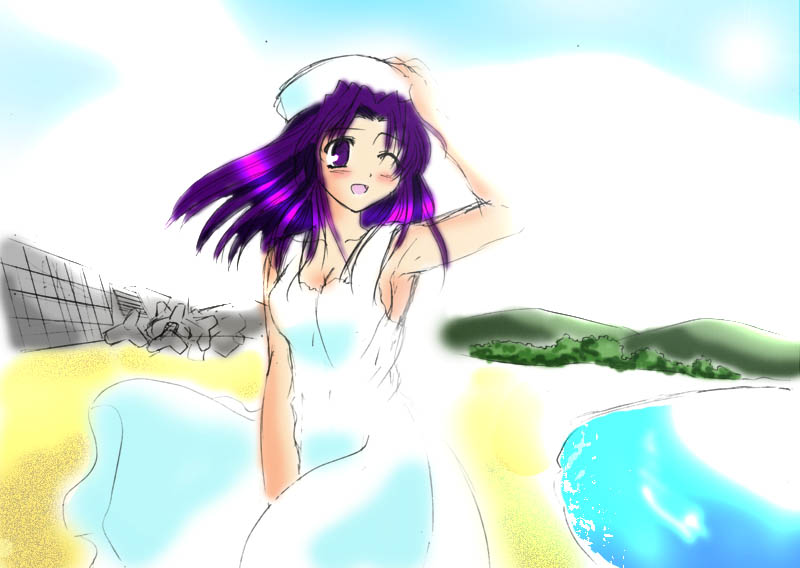
「先輩、大丈夫か?」
「う〜、これじゃあ動けないよー」
「大丈夫。オレしか見てないって」
季節のせいか、場所のせいかはわからないが来た時から今に至るまで辺りに人気はなかった。
「………」
「あ、怒ってる?」
「……その、下はつけてるからね」
「え?」
「………」
「あー、うん」
何か微妙に勘違いされていたみたいだ。
が、そんな言葉が聞けるのはちょっとラッキー。
赤面しているのがすごくいい。
無茶苦茶可愛い。
「うりゃ」
「わっ」
先輩が身動きが取れないのをいいことに、オレは後ろから先輩の身体を抱きしめた。
「わっ、わっ」
あたふたしているが、断続的に風が吹くので両手は動かせないでいる。
「ずるいよ〜」
「オレは生まれつきそうだぞ」
ちょっと得意げに言う。
ずるさには自信があるし定評もある。
自慢してもいいし、吹聴されても大丈夫だ。
「そんなの知らないよ〜」
「だったら……」
だからこんなずるさもお手のものだ。
「これから先輩にはもっともっとオレのずるさを知ってもらうから」
ぴったりと身体を密着させる。
「や、やめてよ、浩平君… これ以上したら悲鳴あげちゃうよ…」
「近くには誰もいないよ」
そう言うと、オレは先輩の帽子が風で飛ばされないようにと指で引っ掛けるようにして手を回した。
「それでも大声で叫べばきっと誰か聞きつけて来るよ」
「叫ばせない」
ゆっくりと顔を近づけてもう一度オレは言う。
「オレはずっと先輩の側に居る。何があっても、必ず最後には先輩の側に居る」
身体を入れかえるように先輩を正面から抱きしめ、かつて誓った言葉を繰り返す。
「………」
「………」
「……絶対だよ」
「ああ」
「二度はないよ」
「わかってる」
「もう……嫌だよ」
「うん」
「約束、だよ」
「まかせとけ」
「もう……」
オレがそう言いきったとき、先輩は緊張を解いた表情になった。
「やっぱり浩平君は、ずるいよ」
そう言って先輩は微笑むかわりに、抱きしめ返してくれた。
六月の海は時には穏やかに、時には激しく波しぶきをあげて背中越しに音の抑揚をつけている。
陽射しの割に少しばかり肌寒く感じる風は、オレ達二人の距離を近づけはしても遠ざけることはない。
同じ景色を眺めることなんかできなくても、今この瞬間オレは好きな人と一緒にいてて、同じ時を楽しみ、同じものを味わっている。
オレはそれを一分でも一秒でも手放したくない。
ほんのひとときでも、失いたくない。
その思いを伝えたくて、それだけが証明の証のようにと腕に力を込めていた。
そしてみさき先輩からも、力が伝わってきた。
彼女も間違いなく、同じ気持ちでいる。
「浩平君…」
「ん?」
「最後には、じゃないよ」
「…今度はずっと、だな」
「うん。そうでないと……嫌いになっちゃうよ…」
「それは困る」
「じゃあ約束…」
「ああ」
そうしてオレ達はキスをした。
指きりをするように。
静かな波の音と緩やかな風を向こうに、オレ達は今までの互いの空白を埋めるようにずっと抱きあっていた。
ふたりの夏は、すぐそこまできていた。
<完>
あどべんちゃら様のサイトの4万HIT記念のイラストに触発されて書いた即興SSの一つです。
これが私の中のみさきSSのスタートでした。
再掲載に当たってあどべんちゃら様よりイラストの転載許可を頂きました。
絵描きにとって昔のイラストを、しかも落書きという形のものをわざわざ引っ張り出されるのは困惑でしょうが、このSSのきっかけとして我侭を言わせていただきました。
快諾してくださったあどべんちゃら様、本当にありがとうございました。